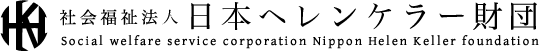ヘレンケラー物語


しかし1歳7ヵ月目に、原因不明の高熱と腹痛におそわれ、一時は医師も見放すほどの重体に陥ったが、医師の努力で辛うじて一命だけはとりとめたものの、耳と目をおかされ、光と音の世界から完全に隔離されてしまった。
幼いヘレンのわずかに記憶に残る言葉といえば、水を意味する「ウォー・ウォー」たった一言だった。それでも母子の間では何とか手ぶり身ぶりで意味は通じたので、両親は希望を捨てなかった。

1887年、当時22歳の妙齢サリヴァンが、タスカンビヤにあるヘレンの家へ来たのは、春3月のうららかな朝だった。ヘレンに会ってみると、7歳になった彼女は予想に反して四肢のすくすくと伸び、リンゴのような頬をした元気のいい子だったのでほっとしたが、一方怒りっぽくて乱暴、いささかも疲れを知らぬようにはね回り、両親も時に手を焼く有様なのを知って、この子に素直さを教えることは並大抵の苦労ではないと直感した。しかしヘレンは、頭脳が極めて明せきで、ことに記憶力がよく、適切な教育により素晴らしい子供になれるとの確信を抱いた。
サリヴァンは着いた翌日から早速教育にとりかかった。まず最初に、パーキンス盲学校から贈られた人形をヘレンに抱かせ、指文字で「DOLL(人形)」という字をその掌に書いた。もちろんヘレンは何のことか判らなかった。繰り返しているうちに、それが自分の抱いているものの名前であることを覚り、この調子で努力しているうち、2週間目にはすべてのものに名のあることを理解するようになった。もともと頭のいいヘレンの進歩は日に日に早くなった。サリヴァンはそれまでの経験によって、点字によるよりも指文字の方が、興味と快感を伴いながら進歩も早いことを知っていたので、最初から指文字による教育をはじめたのである。
教育をはじめて3カ月目、ヘレンはもう300の言葉を覚えた。これはヘレンの天賦の知力にもよるが、サリヴァンの教育的手腕が普通でなかったことを物語るのである。一例をあげると、ある日ヘレンがコップとその中に入っている水を同じものだと主張してゆずらず、遂にサリヴァンとけんかになってしまった。サリヴァンはヘレンの気分を転換させるため、しばらく他のことに興味を移し、その上で初めて戸外に誘い出し、ポンプ小屋に連れて行って、持っているコップに冷たい水を注ぎこんでやった。と同時に「水」と指文字で書くと、瞬間ヘレンの顔色がさっと変り、コップを落して打たれたようにじっと考えこんでしまった。彼女の面にいつもと違う輝きが現れはじめた。自分の誤りが分ったのである。-このことがあってから、あれほど頑固だったヘレンが急に素直になり、サリヴァンの教えをよくうけ入れて、進歩も目立って来たと、サリヴァンの記録に残っている。
かくして相当の言語と知識を教えこむことに成功したサリヴァンは、第二段階の教育方法として、ヘレンに『読む力』を与えることにとりかかった。それは点字ではなく、一つ一つの語を別な紙に凸文字で書いたものを、順序よく並べることによってである。次いで書くことを教えた。ヘレンの知りたいことをよく注意し、教育と生活を近づけ、興味を引き立てながら、独学によって知り得るすべてのものを、教え授けるようにした。これによってヘレンの思想はだんだん整理され、観念の正確さを加えることが出来たと後にサリヴァンは語っている。
そこで1889年10月、ボストンのパーキンス盲学校に赴き、ここでヘレンは生まれてはじめて自分と同年輩の多くの盲児と遊ぶことが出来た。そこで元気にはしゃぐ子供たちが、みんな自分と同じ盲人であることを知った時の驚き、しかも子供たちが実に幸福そうであること知ったヘレンの喜びは筆舌につくし難く、『私はどんなに生き甲斐を感じたことでしょう』と彼女の自叙伝に述べているのを見ても想像できる。この旅行では、ワシントンに行って大統領クリーヴランドに招待されたり、古戦場を訪れたり、生れてはじめて汽船に乗ったりして、生活の内容もだんだん深くなっていった。

1890年、ヘレン11歳の春は、一生忘れ得ない思い出の年である。それは彼女が長い年月、目は見えないとしても、何とかして話したい、語りたいと念願していた、その悲願が達せられたからである。それまでは、例え一言でも声というものを発してみたいばかりに、常に片手で自分の喉を押え、片手を唇にふれて声を出そうと努めてみた。サリヴァンの口中に指を突っこんで話す時の舌の位置を知ろうと努め、そのためサリヴァンが嘔吐したことは一再でなかった。はじめ周囲の人々は、そんな出来もしないことを無理に実現しようとして不成功に終った場合の悲哀を考え、またそれによって指文字や点字による指導が、その進歩を妨げられることを恐れて、容易に手を出しかねていた。しかしヘレンは、当時ノルウェーで聴覚障害者の発声研究が一部成功したことを伝え知って矢も盾もたまらず、サリヴァン先生もその熱意に動かされて、遂にボストンのホレースマン聾学校にヘレンを伴い、校長のサラー・フラー女史に読話と発音法を学ぶこととなった。
ヘレンの自伝を読むと、
『私は校長先生が一言を発するごとに彼女の顔の上に手をあて、その唇の運動や舌の位置を探って、その真似をして、一心に学んだ結果、1時間後には六つの音の要素(M.P.A.S.T.I)を覚えこんだ。かくて私は最初に「It is warm today.(今日は暖かです)」と自分には聞えないながらも、声だけは発し得た時の驚きと喜びは、終生忘れ得ないことです。それは聞き取りにくい言葉ではあった。しかし正しく人間の言葉であった。私はこれで永い間の苦悩から救い出された』
という意味のことを書いているのを見ても、その時の感激が如何に大きかったか想像出来る。ヘレンは更に1894年から2カ年間、ニューヨークのライトヒューメーソン聾唖学校で発声法の研究を積んだが、この時はドイツ人について勉強したので、わずか数ヵ月でドイツ語なら何でも判るようになったという。ヘレンの頭脳が凡ようでなかったことはもちろんだが、明けても暮れても側をはなれずその手助けをしたサリヴァンの献身的努力は言葉ではとうてい語りつくせない。そのころにはヘレンの学問も相当すすみ、ラテン語、歴史文学、地理などには特に興味を持ち、同じ年ごろの男女生徒の優秀なものと同等の成績を得たと、伝えられている

ヘレンの向学心と求知欲はますますおう盛となり、是非とも大学教育を受けたいと熱心な希望をもらしはじめた。幸いある方面から物質的な援助もあって、その準備教育をアイアン博士について家庭ではじめた。ヘレンはハーバード大学を特に希望し、その入学準備のためケンブリッジ市の女学校に入学した。時にヘレンは17歳だった。
ハーバード大学の当時の入学試験科目は英語、歴史、フランス語、ドイツ語、ラテン、ギリシャ両古典及び代数、幾何であった。女学校での教育の受け方は、サリヴァンもヘレンと一緒に登校して同席し、教師の教えるところをサリヴァンがそのまま指文字でヘレンに伝え、また質問する時はヘレンが指文字でサリヴァンに伝え、更にサリヴァンから教師に口でその意味を説明するという極めて不便な方法であった。
ヘレンはラテン語が最も得意で、数学は一番苦手だった。かくて3ヵ年間の大学入学準備期間は、睡眠時間も割いて、文字通り肉をきざみ骨を削る思いの勉強をつづけ、また何度も点字本を読むために、指頭には血がふき出るほどだったという。しかしこの労苦は遂に報いられる時が来た。2回にわたる入学試験の結果、視聴覚障害の身で、しかも優秀な成績のもとに、多年あこがれのハーバード大学附属のラッドクリフ女子大学入学の栄誉を勝ち得たのである。ヘレン21歳の秋、世界歴史始まって最初のことと、当時の新聞はほめたたえたのである。
大学生活4年間のことは簡単にすすめよう。教室での勉強中も、休養の時間中も、夜間他の人々が寝た後もヘレンとサリヴァンは忙しく指先を動かし、あるいはタイプライターを打っていた。ヘレンは古典文学と哲学に特に興味を持ち、そのために他から与えられる学資金も点字本を買ったり、参考書を点字にほん訳する費用のために遣い果したほどだった。
4ヵ年の刻苦精励は当然報いられて、ヘレンは学友のなかでも極めて優秀な成績でラッドクリフ・カレッジを卒業、視聴覚障害者としては前代未聞のバチェラー・オプ・アーツの学位を獲得した。卒業の年、1904年10月、当時開催中のセントルイス博覧会は特にヘレンの卒業を祝して“ヘレンケラー・デー”を設けヘレンを招いて大講演会を開催した。“聴覚障害者がものをいう”奇跡の人、ヘレンの演説を開こうと、大講堂の窓という窓が人で折り重なるほどの大盛況だった。壇上におもむろに進んだヘレンは、生まれてはじめて人前に立ち、力一杯の声を張り上げたつもりだったが、自分ではその声がきこえない。実際に喉から出た声は実に細く、側にいた人が辛うじてきき得る程度だったが、それをサリヴァンを全然通せず、博覧会会長のフランシス氏がそのまま大声で復唱して聴衆に伝えたところ、大講堂にあふれた聴衆は奇跡の実現に大いに驚きかつ感激して、演説を終って退場するヘレンにわっと殺到し、動けなくなる騒ぎに交通巡査が出動して整理しなければならぬほどだった。

ヘレンの社会的活動はただに講演だけではない。今日まで米国内で関係した公共事業は数知れず、また女史の訪問した海外の国々では、女史の来訪を記念して、その国に視聴覚障害者のために幾多の福祉事業が生れ、現在大きく実っている。
女史の著書は、1903年大学在学中に執筆した『楽天主義』と『私の生涯』をはじめとして、1905年随筆『暗黒より出でて』、1908年『私の住む世界』『闇より』、1910年自由詩『石壁の歌』、1927年『私の宗教』、1930年『中流』『私の近頃の生活』、1933年『夕暮の平和』、1938年『日誌』、1940年『われら信仰を持たん』などがあり、何れも発行と同時に障害者はもとより一般からもむさぼるように読まれた。
これらの著書に織り込まれたヘレンの高い思想、人生に希望と輝きを与える数々の著述並に社会的活動によって、最大の名誉が与えられる日が来た。それは米国と英国の二つの大学から学位がおくられたのである。一つは1931年、フィラデルフィアのテンプル大学からの人文学博士であり、もう一つは1932年、英国グラスゴー大学からの法学博士である。前者は一般世論をも考慮して特にサリヴァン女史にも同じ学位を贈ったが、サリヴァンはその資格なしとして辞退し、再三すすめられて翌年ようやくその光栄を受けたことは、サリヴアンの人柄の一端を物語るものといえよう。
ヘレンケラーは平和論者としても知られ、第一次世界大戦以後は、サリヴァンの影響もあって社会事業を唱え、実際運動にも参加して、恵まれない人達のために大いに献身した。また持論である平和主義に立脚して、米国の大戦参加に極力反対したため、一部の人達から中傷され、一時窮境に立たされたこともあった。
その生涯は幾多の苦難に満ちた道だったが、常に明るい希望とたゆまない努力によってのり越えてきた。如何なる苦悩に遭遇しても常に人生に希望を捨てないヘレンの楽天主義は、自ら体得した貴い収穫であり、それに敬けんな信仰心もあずかって、力あるものになったのであろう。

しかし、ヘレンの一生にも悲しい二つの出来事があった。一つはヘレン37歳の夏、一家が経済的に不如意となり、サリヴァン女史も病気療養中の時、臨時に秘書を勤めた年下の一青年から愛の告白をうけ、身も心もとけるような恋の喜びに胸をうちふるわせたことがあった。青春におくれてほころびかけた恋のつぼみではあったが、母の猛烈な反対で悲しい破たんに終り、楽天主義を強く唱えるさすがのヘレンも、失恋の打傷に身も世もあらぬ悲しい幾日かもあった。
もう一つはサリヴァン先生の死であった。先生は寄る年波にはかてず、70歳で貴い生涯を閉じたのである。臨終の枕辺に馳せ参じて、先生の手をにぎりしめたヘレンが、如何になげき悲しんだか。思えばヘレン8歳の春、当時22歳の娘盛りの先生が、はるばるタスカンビヤの家を訪れて以来50年、限りない慈愛と忍耐をもってヘレンをして『世紀の奇跡』とまで育てあげたこの先生、この手こそ瞬時もヘレンの側を離れず、ヘレンの目となり、口となり、耳となり思想を教え、芸術を授け、科学を伝えたその貴い手である。刻々と冷たくなっていく先生のその偉大な手を力一杯にぎりしめて、泣きくずれるヘレンの姿には、並いる者すべて涙せぬものはなかったという。1936年10月20日、木の葉がはらはらと散り初める秋の夕暮であった。
(註)1
「ヘレンケラー物語」の原文は昭和23年9月1日付、ヘレンケラー・キャンペーン委員会及び毎日新聞社発行のパンフレットを参照させていただきました。
(註)2
サリヴァン先生の死後は、ポリー・トムソン女史が通訳となり、昭和30年夏の第三次ヘレンケラー女史来日の際にも付き添ったほか、世界各地の遊説に同行するなど、ヘレンケラーの晩年をよく支えたとして知られます